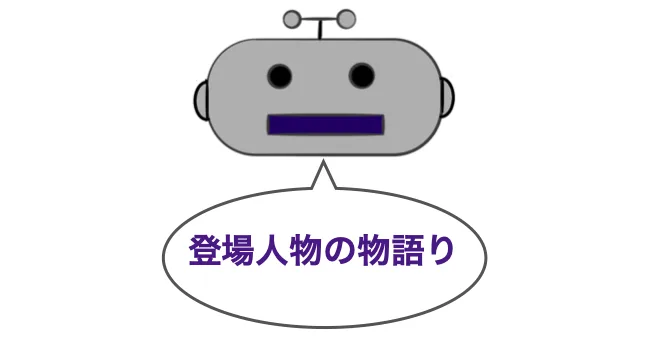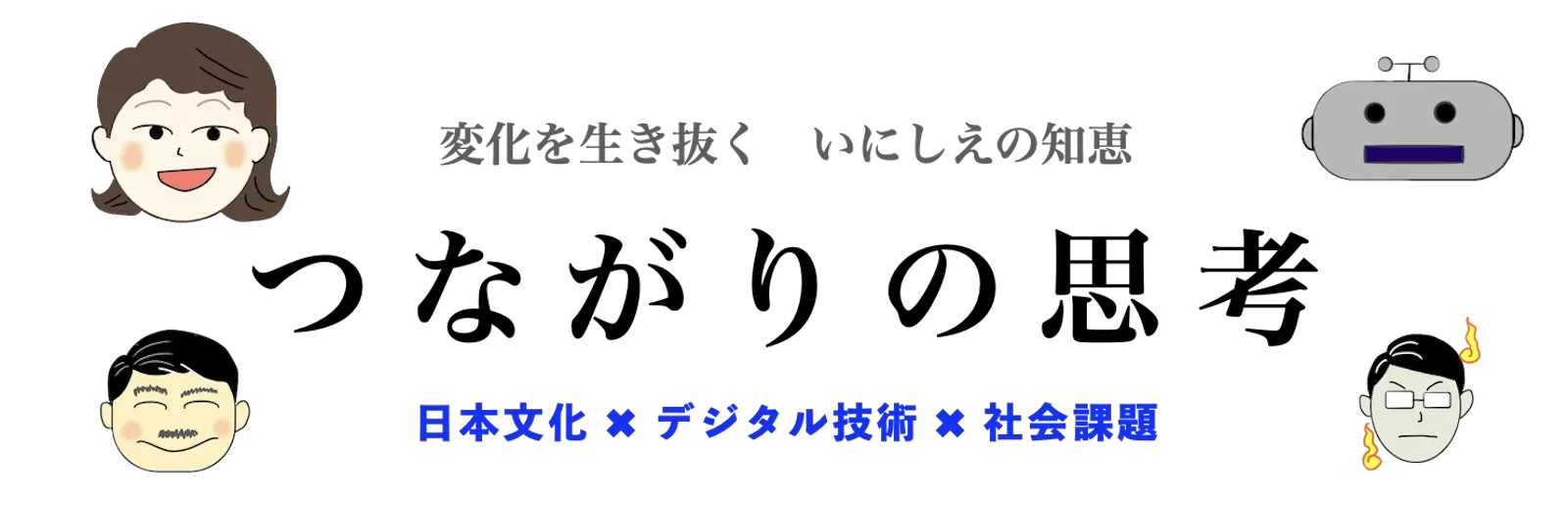-


サンタも鬼もゆるキャラも? 日本文化の“存在生成システム”を読み解く
サンタは実在するか?日本文化が示す「存在」の新しい視点 なぜ、サンタは実在しなければいけないの? 西洋のドラマで、サンタは実在するかしないのか、実在しないから信じない。というシーンを時々見かける。 その感覚に馴染めない、実在することと信じる... -


オタク文化の力:世界を動かす情熱の可能性
オタクとは何か?古今東西比較 オタクってどんなイメージですか? オタクって、アニメとかゲームが好きな人のことですか? 1980年代、日本で「オタク」はアニメや漫画ファンを指す言葉として広まりました。当初は「社会性が欠けた人」というイメージが強か... -


なぜ日本のお助けロボットは「ドラえもん」であって、「ターミネーター」ではないのか?
日本のロボット開発の特徴ー世界が注目する「共生のテクノロジー」 ロボットという言葉を聞くと、どのような姿を思い浮かべるだろうか。 冷たい鉄の身体を持ち、人間の代わりに働く無機質な機械――。 しかし日本のロボットは、少し異なる。どこか人懐... -


忍者ブーム再燃:欧米で忍者が再評価される理由とは?
Ninjaは世界でどう見られている?アメリカとヨーロッパの文化比較 “Ninja, Sushi, and Samurai”(忍者、寿司、侍)、 “Ninja, Zen, and Sushi”(忍者、禅、寿司) これらは欧米で日本文化を紹介するコンテンツでよく見られる表現だそうだ。 現代の海外の忍... -


「ものづくり」とは “つながり” である|人・自然・モノが紡ぐ日本文化の本質
日本の「ものづくり」とは?──単なる製造ではない “つながり” の哲学 日本の物作りは、合理性だけでは語りきれない。 「ものづくり」とは単なる製造ではなく、素材とのつながり、作り手と使い手の関係、さらには物を介した人々の絆を含めた深い概念である... -


桜が散る瞬間、なぜ心が動くのだろうか?
散りゆく桜に込められた想い―日本人が慈しむ儚さの真髄 自然の猛威はあらゆる物を破壊し、人の心に無常感を植え付ける。 負のイメージの強い無常感だが、日本の文化の中では様々に変化した。 移ろうことを愛で、儚さを慈しむ風習が生まれた。 日本は地震多... -


AI時代の挑戦:100歩先行く唯一無二の可能性
100歩先行く 変化の時代 変化の早い現代に、我々はどう対応すれば良いのだろう? 「1歩譲る」という言葉がある。しかし、現代では「1歩」とはほとんど言わない、「100歩」と言う。 TVを見ていても、ドラマでも、バラエティーでも、「一歩」... -


合理性を超えて、感性と本能で広がる未来へ
スマホなしで生きられる?システムと人間らしさの関係 人は古来より安全で便利な生活を求め、それを実現するためにシステムを構築してきた。例えば、鉄道や交通網などは合理的なシステムで成り立っている。しかし、『荘子』は機械(システム)への依存が自... -

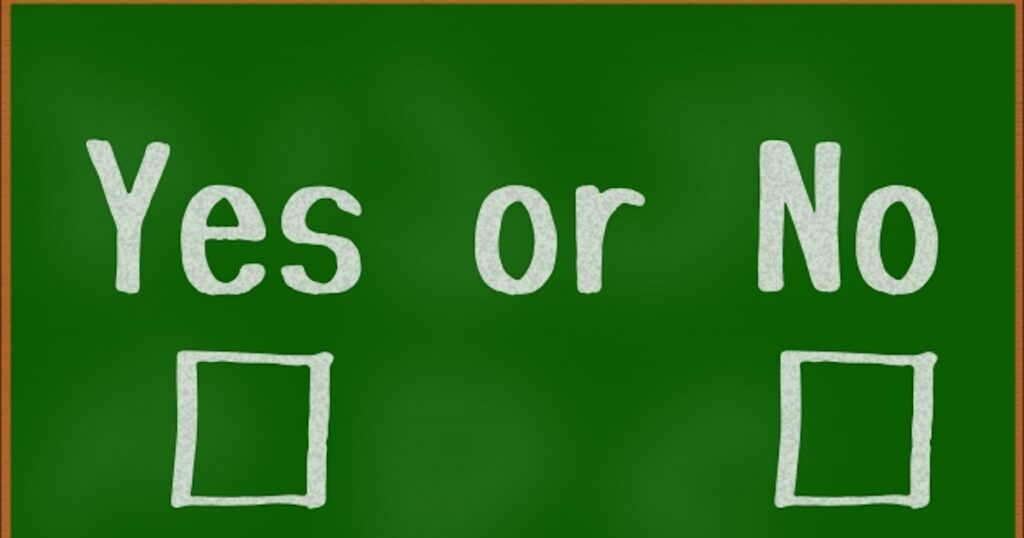
グレーゾーンが鍵!多様性を尊重する日本の価値観
曖昧さは弱さか?日本文化に隠された柔軟性の力を探る 西洋においては自己の確立が重要視され、自らの存在を明確にし、アイデンティティーを構築することが求められる。一方で、日本では個人の確立よりも関係性の中で自己を見出すことが重視され、自己を明... -


つながりの思考で実現するサステナブルな社会
コントロールの限界:気候変動と文明発展の関係性 地球の歴史において、この数千年は比較的穏やかで、変動の少ない時期であったという。その穏やかな環境の中で、人類は物事をコントロールし文明を作り上げた。 コントロールの本質は、物事を効率的かつ効...